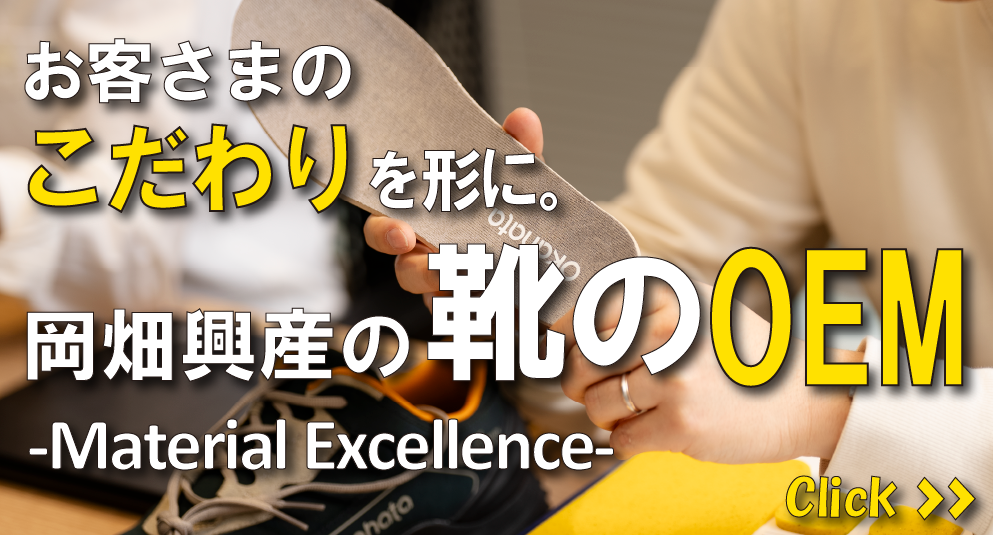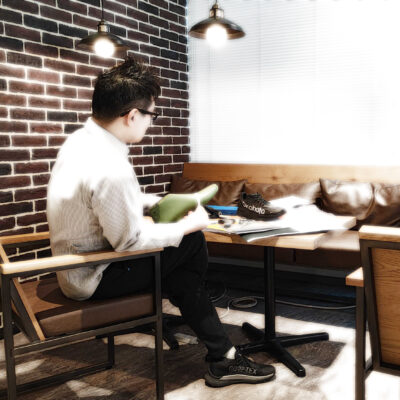こんにちは、岡畑興産のソメヤです。
皆さん、突然ですが、ウレタンゴムってどんなゴムかご存じですか?
「聞いたことはあるけど詳しくない」という方も多いと思いますが、実は、ウレタンゴムとは”ゴム”ではないんです。
「どういうことだ!?」と気になってきませんか?
ウレタンゴム素材を使ったものは実は身の回りにあり、私たちの暮らしに役立ってくれています。
今日はそんなウレタンゴムについて、紹介していきます!

目次
ウレタンゴムとは?
「ウレタン」はポリウレタンの略ですが、このウレタンはフォーム(発砲)と非フォーム(エラストマー/人口皮革や合皮/弾性繊維/塗料/接着剤など)に分かれています。
ウレタンゴムとは、この非フォームであるエラストマー(ゴム状の弾性体の総称)の1種を指します。ウレタン全般について「ウレタンの特徴とは?種類やどのようなシーンで用いられるかご紹介」でもご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
冒頭でも触れた通り、ウレタンゴムは実はゴムではなく、正式には、”ゴムのような弾力を持ったプラスチック”なんです。
ゴムと似た性質を持つので、JISでも合成ゴムとして分類されていて、ゴムの種類を示す記号では”U”と記されます。
そのため、合成ゴムの一種とされていることもあります。また、ウレタンゴムは「ポリエステル系」と「ポリエーテル系」の2種類があります。
ポリエステル系は耐油性が優れている反面、加水分解しやすく、ポリエーテル系はポリエステル系の反対の性質を持ち、機械的強度が高いのが特徴です。
ウレタンゴムのメリットデメリットや天然ゴムとの違い
それではもっと詳しく、ウレタンゴムの特性のメリットやデメリット、天然ゴム余の違いも確認していきましょう。
ウレタンゴムのメリット
ではウレタンゴムのメリットといえる特性からご紹介します。
耐摩耗性が高い
他の合成ゴムに比べても、非常に高い摩耗耐久性を持っており、前述したポリエステル系とポリエーテル系ではポリエステル系が耐摩耗性により優れています。
機械的強度が強い
機械的強度とは、引張強度や引裂強度などが優れているということです。
特に引裂強度は、他のゴム素材と比較すると、二トリルブタジエンゴム(NBR)/クロロプレンゴム(CR)5~25Mpa、天然ゴム(NR)が3~35Mpaなのに対し、ウレタンゴムは20~45Mpaと、数値比較でも優れていることがわかります。
耐油性が高い
他の合成ゴムと比較して高い耐油性を持っています。そのため、油と使用しても影響を受けにくいです。さらに言うと、ポリエステル系とポリエーテル系では、ポリエステル系の方が耐油性に優れています。
耐過重性が高い
圧縮永久ひずみ※にも優れているため、荷重による変形などが比較的少ないとされています。
※圧縮永久ひずみ=一定の圧縮率で圧縮した後に、その変形が元に戻らない状態のことや、その比率を表したもの
弾性体である
弾性、柔軟性が高いという性質を持っています。
耐光性、耐オゾン性が高い
光による劣化や変色にどれだけ耐えられるかを示す性質です。
一方、オゾンによる劣化や物理的性質の低下に対する抵抗力を指します。
そのため、野外用途に有効な素材でもあります。
比重が一般的ゴムより比較的軽い
天然ゴム1.1~1.3、スチレンブタジエンゴム1.1~1.2、スチレンブタジエンゴム1.2~1.4
クロロプレンゴム1.3~1.6に対して、ウレタンゴムは1.0~1.3です。
数値を見るとわかりますが、比較的軽いという感じです。参考ですが比重1は水です。1以上は水に沈み、1以下の場合は水に浮くと思ってください。
加工が容易
加工が容易であるため、ウレタンゴムの加工方法は幅広く、注型加工、射出成型、プレス成形などあります。
加工方法の詳細は、後ほどご紹介します!
ウレタンゴムのデメリット
ではウレタンゴムのデメリットといえる特性もご紹介します。
水分に弱い
ポリエステル系ウレタンゴムは、結合分子内に「-COO-」を持っており、この分子構造がH2O(水)と反応して「-COOH(酸)」と「-OH(アルコール)」に分解されてしまうため、水分に弱いです。
この分解のことを加水分解といいます。
ちなみにポリエーテル系ウレタンゴムは、結合分子内に「-O-」を持っており、H2O(水)には影響されにくいといえます。
耐熱性、耐寒性が弱い
一般的ウレタンゴムは耐熱温度80℃程度とされています。
耐寒温度もマイナス30~60℃ほどで、他の合成ゴムの中では比較的劣ります。
「ポリエステル系」と「ポリエーテル系」の2種類の比較では、ポリエーテル系ウレタンゴムの方が耐寒性において優れています。
天然ゴムとウレタンゴムの違い
天然ゴムは、文字通り天然素材であるゴムの木から出る樹液を凝固して作られています。
天然ゴムの特徴としては、機械的強度、反発弾性、耐摩耗性に優れていて、耐熱性、耐オゾン性、耐候性に劣る点が挙げられます。
対して合成ゴムの一種と分類されるウレタンゴムは、石油を原料として、人工的に生産されたゴムです。
現在市販されている合成ゴムは100種類以上あると言われており、用途によっての要求を満たすための配合の違いなどがあるようです。
ウレタンゴムの用途をチェック!

ウレタンゴムは、機械的強度や加工性の高さなどの性質を活かし多用途に使われています。
・工業用品としてのベルトコンベアのベルト、パッキン、ライニング、カップリングなど
・繰り返し使うローラー(紙送りローラー等)
・履物パーツとしてシ一般シューズ、スキーブーツ
・電気パーツ(高圧パッキン)
・フォークリフトやジェットコースターなどのソリッドタイヤ、キャスタータイヤ
・断熱材・振動防止材などの建築材料
・家具・寝具・スポーツウェアなどの日用品
こうやって挙げてみると、その特性を活かして幅広い用途に使われているのがわかりますね。
ウレタンゴムの種類も詳しく!種類の違いを解説
すでに前述にてウレタンゴムの種類はポリエーテル系とポリエステル系があることを記載していますが、もう少し詳しく追記します。
ポリエーテル系とは
ポリエーテル系は結合分子内に「-O-」を持っています。
この分子構造により「H2O(水)」に影響されないため、加水分解が起きにくいです。
ポリエーテル系のポリエーテルジオールを原料にしたポリウレタンゴムを「ポリエーテルウレタンゴム」と呼びますが、耐寒性が優れ、加水分解が起きにくい特徴を持ちます。
ポリエステル系とは
ポリエステル系は結合分子内に「-COO-」を持っています。
この分子構造は「H2O(水)」と反応して、-COOH(酸)と-OH(アルコール)に分解され、この化学反応が加水分解になります。
そのため、ポリエステル系のポリエステルジオールを原料にしたウレタンゴムは、機械的強度が高く、耐油性が非常に優れていますが、加水分解による劣化があります。
※ただし近年ではエステル系でも以前に比べて耐性が上がっているものがあるようです。
靴のソールにはよくTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)という材料が使われますが、このTPUにももちろんポリエステル系・ポリエーテル系が存在します。
靴でよく起こる問題の一つである加水分解を恐れ、「耐水性の高いポリエーテル系なら加水分解しにくいし、ポリエーテル系を使えば良いのでは?」という意見もあるかと思います。
しかし、ソールに求められる性能ですと、ポリエステル系に勝っているのは加水分解しづらいという点だけで、ポリエステル系の方がほとんどの面で優れているのです。
このように、求められる場面が全く違うので、同じウレタンゴムといっても、特徴にあった系統の材料を選択することが重要です。
ウレタンゴムの加工方法も詳しくご紹介
ウレタンゴムの加工方法には、注型加工、射出成型、プレス成形などあるとお伝えしましたが、その詳細もご説明します。
注型加工
液状ウレタンゴムの原料と硬化剤を混ぜたものを熱した金型に入れ、一次加硫、その後二次加硫として一定期間熟成させて、バリ取りの処理をして完成させます。
金型の製作費が比較的安く、複雑な形状に対応する一方で、生産性は劣ります。
射出成型
熱で溶かしたペレット状のウレタンゴムを金型に注入して成型する加工方法。
金型代は高いですが、制作単価が安いため量産に適しています。
プレス成型
金型にセットしたミラブルウレタンゴム(加硫剤を加えて練り上げたウレタンゴム)の生地をプレスして成形する加工方法。
生産性が高くインジェクション成型に比べると金型の投資を抑えられます。
ゴムに加硫剤を加えて練り上げたウレタンゴムの加工
次の2つの加工が代表的です。
・切削加工/旋盤加工
ワークに刃物を直接あてて加工する方法です。
切削加工は、固定したワークを刃物のついた工具で切断、穴あけ、削りなどを行う加工で、旋盤加工はその反対に、回転するワークを刃の付いた工具で加工します。
金型を使用しないため、金型製造にかかるコストや期間が節約できますが、基本的に1つずつ加工するため、大量生産には不向きといえます。
・ライニング、焼き付け加工
ウレタンゴムを金属などの表面や内側に接着剤や熱で定着させる加工方法です。
主に金属の保護や摩擦を高める目的で行い、工業用機械のローラーやキャスター、ソリッドタイヤ、ゴムリング、ゴム筒などに用いられます。
ウレタンゴムの特性を知って上手に活用を!
繰り返しになりますが、ウレタンゴムは実はゴムではなく、ゴム状の弾性体の総称(エラストマー)のことで、”ゴムのような弾力を持ったプラスチック”を指します。
耐摩擦性や機械的強度に優れていて、長期の利用でも劣化しにくいというメリットがありますが、水分に弱いという性質も持つ素材です。
また、ゴムではないですが「合成ゴム」の一種として扱われることも多いです。
靴の世界では、実はウレタンゴムをそのまま使うという話はあまり聞きません。
用途としては、工業用部品や自動車部品、家具や寝具、スポーツウェアなどに使われることが多いです。
このように、一口にゴムといっても、天然か合成かブレンドかで違いがあり、さらにその合成ゴムの中にも数々の種類のゴムがございます。
身の回りのゴムが使われている製品を見渡してみて、どんな種類のものなのか調べてみるのも面白いかもしれないですね。
ゴム製品を購入する際も、どんな特徴があるかを知って、用途に合わせてご活用ください!
岡畑興産では、真面目に靴を作っている会社のブログ「くつナビ」を運営しています。
靴や靴の素材、豆知識などさまざまな知識を発信していますので、こちらもぜひご参考くださいね。
※岡畑興産株式会社は、化学品事業と靴受託事業が連携し、機能性素材の材料開発・用途開発を進めています。