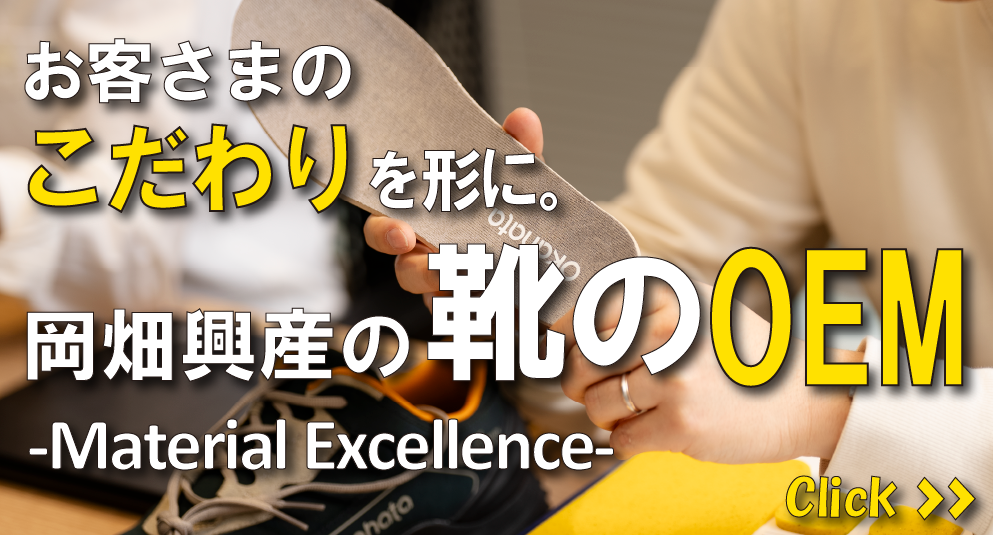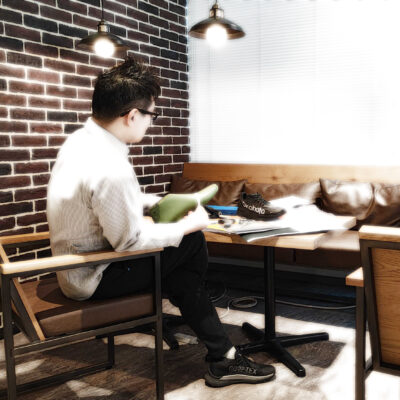こんにちは、岡畑興産のそめやです。
私は仕事の生業上、木型製作や修正なども行うため、木型についての知識が豊富にあります。
靴にとって、木型は無くてはならない重要な存在です。
特に、オーダーメイド靴の場合は細部の修正が必要で、良い靴を作るためには木型が決め手となります。
今回は靴作りのパートナーといえる、木型についてのお話です。
種類や寸法の詳細もお伝えしますので、ぜひご一読ください!
靴の木型とは?目的に合わせて使用される素材の種類は異なる

冒頭でもお話しした通り、木型は靴を作る上で無くては始まらない重要なツールです。
木型によって靴のシルエットやサイズ、履き心地が決まります。
近年では木型は「靴型」「ラスト」などいくつかの呼び名がありますが、木型と呼ばれるのはもともと材料が木製であったためです。
「ラスト」は、英単語LASTの意味である最後からついた呼び名ですが、靴の出来は最終的に木型で決まるといわれたことからそう呼ばれるようになったようです。
また、靴型は「靴を作る型のため靴型」ともいわれています。
木型の製作には多くの知識と経験が必要で、モデリストと呼ばれる木型製作技術者が製作します。
靴の大きなメーカーの場合は社員としてモデリストがいることもありますが、一般的には木型屋といわれる木型製作専業会社にモデリストが所属しており、オリジナルのモデル木型製作を行っているケースが多いです。
オリジナルの木型で靴の試作を重ね、量産決定の暁には「生産用木型」を靴メーカーから木型屋へ発注され、木型屋で生産されます。
靴の生産にはプラスチック製木型が使われることが多い
モデル木型は現在でも木製が主流ですが、生産する際の生産用木型は「プラ木型」と呼ばれるプラスチック製木型が主流です。
昔は生産用木型も木製でしたが、産業発展とともに、より安価で加工しやすく、変形しにくい素材として、プラスチック製が主流になりました。
ちなみに木製は十分に乾燥させてから使用されますが、木の性質上、湿気により膨張したり縮んだりの影響により、数年経つと3MM程度の寸法ずれが発生するケースもあります。
プラスチック製については木製に比べ、外的影響が軽微であり、靴型として安定した素材といえます。
これを聞くと「プラ木型優秀じゃん!モデル木型は何で木製が多いの?」という疑問が出てきますね。
参考までにですが、主にモデル木型は靴のパターン製作に使われます。
パターン製作は木型に靴のデザインを描いたり、テープを貼ったりする必要があるほか、滑りにくいため、木製が適しています。
プラスチックはつるつるで滑りやすく、鉛筆でのデザイン線も乗らず、テープを貼ると剥がしにくいなど、パターン製作では扱いにくいのです。
ただし、メーカーによっては、すべて木製ではなくプラ製で使うこともあります。
靴の木型にはどんな種類がある?
木型はプラスチック製も使われるとお話ししましたが、そのほかアルミ製もあります。
また、素材以外にも種類があります。
モデル木型は単一構造のソリッドラストとして製作するのが一般的ですが生産用に使用するプラスチック木型については、構造(形状)の種類があります。
靴は木型にアッパーとソールをぴったりと密着して製作するのですが、靴から木型を取り出すことは、履き口の狭さを考えると非常に難しいです。
そのため、製作後に靴から木型を抜く際、靴に極力負担をかけずに木型を抜く目的で、いくつかの構造が考えられました。
では、改めて素材の種類ごとの特徴と、構造の種類についてお話ししていきます!
木型の素材の種類
木材製
プラ製ができるまでは木製が主流でしたが、現代では木製はモデル木型の場合がほとんどです。
また、木製は木材なら何でも良いというとそうではなく、硬い木が使われます。
一昔前なら適度な油分と硬さのある、樹齢50年以上のミズメという木が使われていましたが、手に入らなくなり、現在では西洋シダが使われているようです。
プラスチック(ポリエチレン樹脂)製
前述しましたが、一般靴工場で生産用に使われる木型はほぼプラスチック製です。
樹脂製品といえば射出成型を思い描くかもしれませんが、プラ木型の場合はあらかじめ射出成型で大きな状形で成形されたものが木型屋に届き、その状態を機械で削りだして、各モデル木型に合わせて削られます。
モデル木型は頻繁に製作しますので、射出成型金型をモデルごとに製作すると、投資金額がかなり大きくなるからです。
採算が取れなくなるため、汎用型ベースのみ射出成型で作り、そこからは専用機械で削り出します。
削る機械にはモデル木型の3Dスキャンデータが取り込まれており、自動でその形状に削ってくれます。
ただし完全自動とはいかず、爪先、かかと、それ以外も人の手によって仕上げ工程が入って完成するものです。
アルミ製
主にゴムを加硫する靴の製品に使われます。
皆さんが良く知っているコンバースのオールスターのようなバルカナイズ製法の場合に使われる木型です。
靴の成形は加硫缶に靴を入れるのですが、缶の中は120度くらいの温度で1時間程度入れることで、ゴムが加硫されます。
その際に靴にしっかり熱が伝わるよう、木型に熱伝導率の高いアルミを採用しています。
木型の構造の種類
ソリッド
木型の形状のまま製作されたもので、木型を分けたりせず、そのままの形で製作された木型です。
モデル木型はほぼソリッドで制作、またスニーカーの様に爪先まで紐を通すデザインなどは、紐を抜くことで靴の開く部分が広がる為、ソリッド木型が使われたりします。
中折れ式

木型上部真ん中あたりをV字にカットされている外観が特徴で、中折れという名の通り、木型の真ん中でパカンと曲がり、ジャッキに固定して木型を折りながら、かかとから木型を抜きます。
この方式は木型を抜く際に踵上履き口に多少負担がかかりますが、日本の靴工場では多く採用されている方式です。
スライド式
木型の真ん中あたりで切断し、爪先に対して、踵側がスライドする構造。
木型の真ん中上に向けてスライドするため、木型の全長が短くなり、靴に負担をかけずに、靴から抜くことが可能です。
海外の靴工場では多く採用されている木型です。
甲切式

木型の甲部のみを切り取り式にした木型で、靴から木型を抜くときに、甲部を取り外す構造。
甲部がないので、木型が取りやすくなります。この状態で木型に空いた穴に型抜き棒を使って靴から抜き取ります。
上記の4つ以外に「割型」といわれる方式の木型もありますが、現代で使用されているのを見たことがありません。
主流はあくまでも上記4つとなります。
オーダーメイドの靴は木型の寸法が重要!
簡単にいうと、靴は木型にアッパーをぴったりと密着させてソールを貼ります。
木型に対してぴったり付いているということは、木型を抜いた靴の内径と木型の体積とは限りなくイコールとなります。
つまり、靴を履いた際のフィット感、履き心地、また靴のシルエットは、木型の設計やシルエットが大変重要です。
人の足を測定分析し、人の足の形状とシューズの見た目としての形状が融合したものが、木型の正体なのです。
そのため、オーダーメイド靴を作る際には木型が要となり、お客様の足の寸法を測定した上で、オリジナルの木型を用意します。
まず、保管している既存木型内でお客様の足の寸法に近いものを準備し、その木型を数値に近いものにアレンジ(足したり減らしたり)して、「仮縫い靴」という試し靴を製作します。
さらに、仮縫い靴を履いた状態を見た目と触診でチェックし、履いた状態についてもお客様の意見を聞き、木型をさらにフィットするよう修正。
そのような工程を経て、オーダーメイド靴が完成します。
この製作方法により、既製品では味わえないフィッティングを実現した、あなたの足だけの靴が完成します。
オーダーメイドの靴は非常に高額ではありますが、手間暇をかけて製作される故の価格なのです。
木型メーカーさんへ訪問し、木型について丁寧に教えていただいた「くつナビ新入社員工場訪問研修レポ/かげやま、ラスト工場行ったってよ」も、ぜひ読んでみてくださいね!
オーダーメイドに限らず、靴のフィット感はとても大切です。
こちらのブログも、ぜひ参考にしてみてくださいね!
靴のフィット感は大切!その理由やサイズの測り方、選び方をチェック!
靴作りは木型の種類も重要!今後の素材の進化にも注目
ここまでお読みくださった皆さま、お付き合いありがとうございます。
靴の木型については、ネットを検索してもあまり詳しい情報は出てきません。
それだけマイナーな内容であり、靴のメーカーにいても木型に携わる業務をしないと詳しくは知らない場合が多いのが現状です。
靴の制作において木型は核となるツーリングであることがご理解いただけたと思います。
しかしながら、木型=フィッティングは必ずしもイコールではないことを付け加えておきます。
現在の靴は素材進化(ソール、インソールのクッション性、柔軟なアッパーマテリアル)により、フィッティングに影響することが多いからです。
靴は木型、マテリアルの総合によりフィッティングが決まります。
木型以外にも重要な要素はあると思ってください。
それでは次のブログでお会いしましょう~!
岡畑興産では、真面目に靴を作っている会社のブログ「くつナビ」を運営しており、靴や靴の素材、世界の市場についての豆知識など、さまざまな知識を発信しています。
ぜひ、他のブログも読んでみてくださいね!
※岡畑興産株式会社は、化学品事業と靴受託事業が連携し、機能性素材の材料開発・用途開発を進めています。